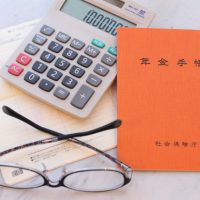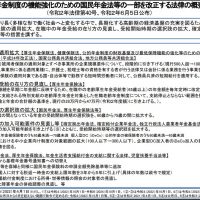自営業者(個人事業主・フリーランス)等が所得税や住民税を節税しながら退職金・老後の生活資金を積み立てることができる定番の制度として、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「小規模企業共済」があります。
常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主・フリーランスや法人代表者・役員が加入できます。
卸売業・小売業やサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主・フリーランスや法人代表者・役員が加入できます。
掛金は月額1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選べ、増額・減額もできます。
掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選べます。
掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象となります(社会保険料控除と違って、本人分以外の掛金を払っても控除の対象にはなりません)。
掛金の前納もできます。前納月数に応じた割引(前納減額金)を受け取れます。
1年以内の前納掛金(-前納減額金)も、課税対象となる所得から控除できます。
加入時の年齢制限や満期はありません。
個人事業主・フリーランスが加入した場合は、掛金納付月数6か月以上で、次のいずれかの事由が生じたときに共済金を受取ることができます。
【共済金A】・すべての個人事業を廃止した
・死亡した
【共済金B】・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ)
共済金の受け取りは、一括受け取りまたは分割受け取りを選べます(要件を満たせば、一括受け取り・分割受け取りの併用も選べます)。
一括で受け取った場合は退職所得扱いとなり、分割で受け取った場合は雑所得扱い(公的年金等控除の対象)となります。
このように、掛金を払う際も、共済金をもらう際も所得税・住民税の節税となります
死亡による共済金はみなし相続財産として相続税の課税対象(ただし、法定相続人×500万円までは非課税)です。
掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で事業資金等を借り入れることもできます。
なお、掛金納付月数240か月未満で任意解約した場合の解約手当金は掛金合計額を下回ります(掛金納付月数12か月未満の場合は、解約手当金や準共済金は受け取れません)。
共済金等の予定利率は2020年度現在1%です。
中小機構のホームページ (https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html)で、将来受け取れる共済金と節税効果をシミュレーションできます。
加入の申し込みは、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会、金融機関の窓口で行います。