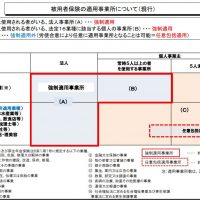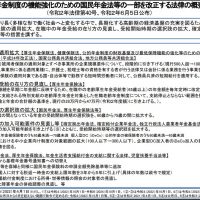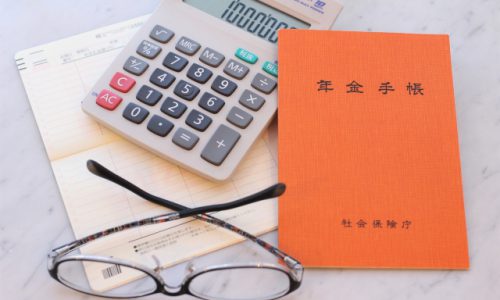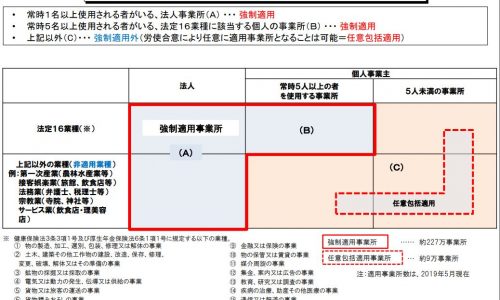法人を設立した際の年金・医療保険関係の手続きは、次の通りです。
もくじ
厚生年金保険・健康保険に加入する手続きを行う
法人事業所が加入するための届出(「新規適用届」)および法人代表者等が被保険者となるための届出(「被保険者資格取得届」)が必要です。
配偶者、子等健康保険の被扶養者になる人がいる場合は「健康保険被扶養者届」(が国民年金の第3号被保険者となる20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は「国民年金第3号被保険者届」兼用)が必要です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入する場合、これらの届書は日本年金機構(年金事務所)に提出します。
電子申請も可能です。
詳しくは日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)を確認するか、事業所を管轄する年金事所(https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)にご照会ください。
(注)
健康保険は、中小企業・小規模企業の場合全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険に加入することが一般的ですので、ここでは全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入するケースについて解説しれます。
しかし、ほかに、業種ごとなどで設立されている健康保険組合が運営する健康保険もあります(例:関東ITソフトウェア健康保険組合、東京都情報サービス産業健康保険組合、出版健康保険組合等)
保険料や保険給付の面で全国健康保険協会(協会けんぽ)よりも有利な健康保険組合もあります。
健康保険組合への加入手続きや保険料・給付などについては、各健康保険組合のホームページを確認するか、各健康保険組合にご照会ください。
国民健康保険をやめる手続きを行う
法人で健康保険に加入した人(被保険者およびその被扶養者)は、国民健康保険の被保険者資格を喪失します(健康保険の被保険者・被扶養者となった日の翌日に国民健康保険の被保険者資格を喪失します)。
市町村・都道府県が運営している国民健康保険に加入している場合であれば、世帯主が14日以内に市町村に国民健康保険の被保険者資格喪失手続きを行う必要があります。
国民健康保険の資格喪失届の提出が遅れてしまうと、健康保険料と国民健康保険料を二重に支払ってしまうこともあります。また、健康保険に加入しながら国民健康保険の保険証を使ってしまった場合は、国民健康保険が負担した医療費を全額返す必要があります。
国民健康保険の被保険者資格喪失手続きを忘れないようにしましょう。
詳しくは市町村のホームページを確認するか、市町村の国民健康保険担当課にご照会ください。
(国民健康保険組合に加入している人の資格喪失手続きについては、市町村ではなく、国民健康保険組合にご確認ください)
国民年金については手続き不要
法人で厚生年金保険に加入した人は、国民年金の第2号被保険者となります(原則として65歳まで)。
国民年金の第2号被保険者となった人の被扶養配偶者(年収130万円未満等の要件を満たして健康保険の被扶養者となった配偶者)で20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険となります。
どちらの人も、国民年金の被保険者資格を喪失するわけではありません。
20歳以上60歳未満で国民年金の第1号被保険者であった人が、国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者へと、国民年金の被保険者種別を変更されるべき場合、法人で被保険者資格取得届や国民年金第3号被保険者届(被扶養者届)を提出することにより、自動的に国民年金の種別は変更されます。
市町村に対して国民年金をやめる手続きを行う必要はありません。
国民年金保険料をまとめて前納しているため払い過ぎの国民年金保険料がある場合は、後で返還の案内が届きます。
(注)同居の親族以外の従業員を雇用している場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要となります。詳しくは、事業所を管轄する労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)にご照会ください。